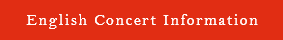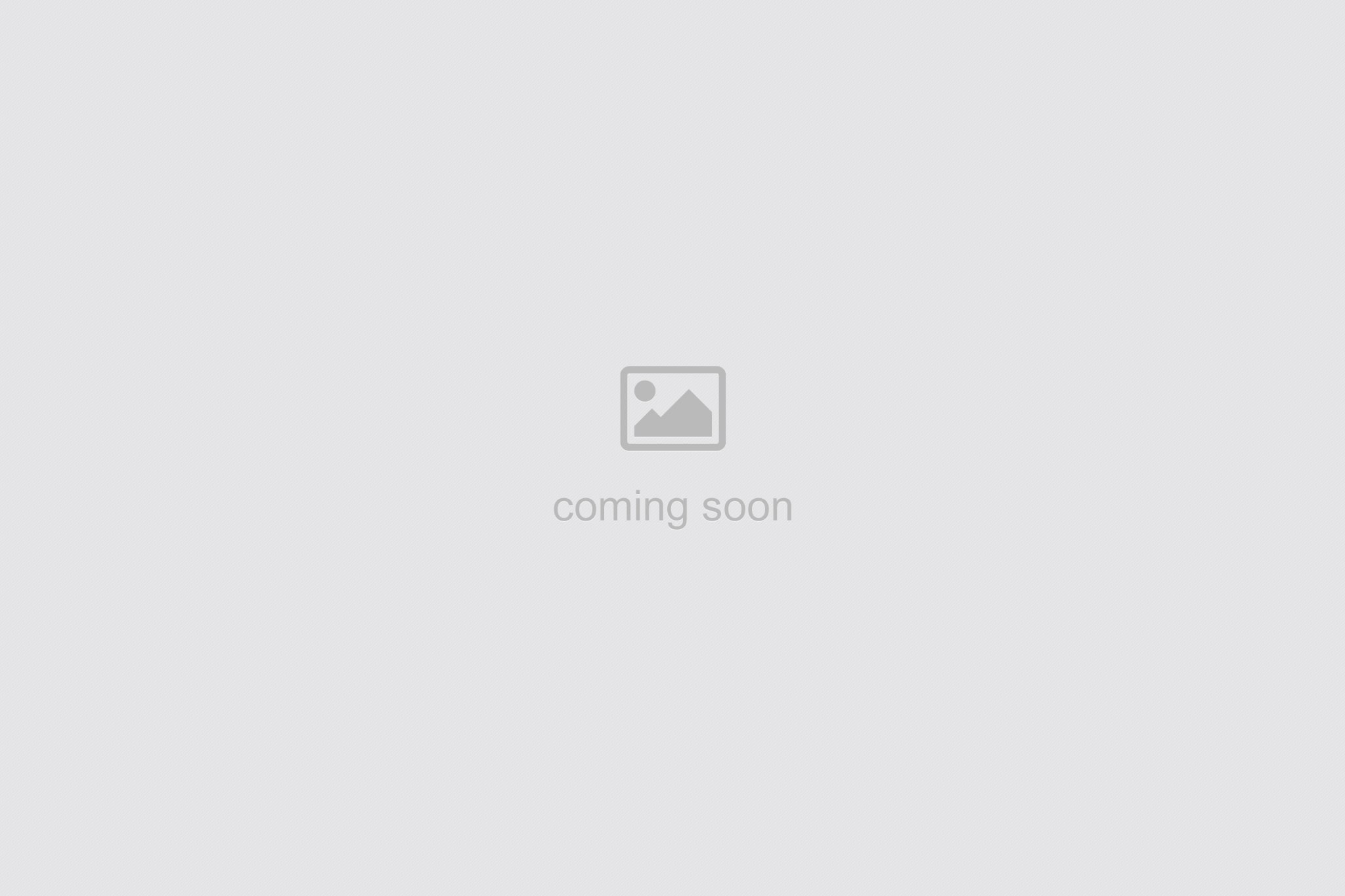エッセー(2017)
第九エッセー2017
2017-12-22
第九 エッセー
「おお友よ、このような音ではなく!」 ~第九が届けてくれるもの
初めて「第九」を知った中学生の頃、変な曲だと思った。実は今でも少し、そんな風に思っている。
第4楽章まで聴き進んで来て、その始まりの部分で第3楽章までの音楽はかき消されてしまう。チェロとコントラバスの忙しないモノローグによって。そして音楽が動き始めたところでバリトンが歌い出すのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この言葉は実はシラーの原詩にはなくて、ベートーヴェンによって書き加えられたものである。言うまでもなく「第九」の最高潮は合唱が始まるここからだ。でもそれなら今までのは何だったのだ。ベートーヴェンはなぜ今までの音を否定するのだ。
「第九」はそんな厳しい否定の精神によって成り立っている。この厳しさに作品の本質を見る人たちの中には、日本では年末の風物詩となった「第九」に違和感を覚える人もいるという。日本人はベートーヴェンの魂と本当に向き合っているのだろうか、ということだろう。だが、見方を変えればこれほど「第九」が演奏されている国は世界にもないのであって(毎年、大晦日にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が演奏しているが)、日本に住む人はけっこう、ベートーヴェンの魂と向き合っているのだ。おそらくはその厳しい否定の精神ともども、僕たちは「第九」を愛しているのである。
ベートーヴェンが否定したものとは何か。この作品が書かれた当時、彼の周囲にあったものを考えてみる。その青年時代は、ゲーテ、シラーらによって打ち立てられた文学運動シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)と時期が重なっている。フランス革命とナポレオンの台頭、その死に至る一連の出来事は激しく彼の心を揺さぶったことだろう。そこに芽吹いたのは近代的な「市民」の意識である。神の時代は終わり、王の時代も過ぎ去ろうとしている。人は人として認められなければならない。それを呼びかける曲を書く時に、ベートーヴェンは自分が今立っている場所を明確に宣言したのだ。自分と世界の「これまで」を厳しく否定することで、「これから」の世界に踏み出そうとしたのである。第4楽章はその実現なのだ。
僕自身がこの作品に覚えるわずかな「変さ」は、おそらくはこうしたベートーヴェンの理念自体が、作品からはみ出してしまうほどの巨大な力を宿していることによる。その力が全容を現す瞬間が、まさにあの言葉なのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この作品が初演されたのは1824年。その時代背景を思う時、あらためて気づかされるのは、人間が自由というものを手にしてからまだ200年ほどにしかならないという事実である。しかもそれはまだ途上なのだ。そしてベートーヴェンその人について言うならば、この曲が完成された当時、彼は完全に聴力を失っていた。音楽家としてはもちろん、ひとりの人間として社交の機会を閉ざされたその寂しさはどれほどであっただろう。だからこの曲は、彼の人を恋うる曲でもある。無音の孤独の淵から人々に向かって微笑みを投げかける、ベートーヴェンの心の歌なのだと思う。
この作品と新鮮な形で向き合おうとするならば、あなたは少しだけ背筋を伸ばしてみるのがいいかも知れない。そして自分の心の中を少し整理して客席に座ってみる。そうすればなぜこの曲が年の瀬にこんなに愛されるのか、よくわかると思う。
「おお友よ、このような音ではなく!」その言葉がもし、わずかに重さを伴ってあなたの元に届いたとしたら、あなたもきっとベートーヴェンの魂に触れているのだ。
この言葉は実はシラーの原詩にはなくて、ベートーヴェンによって書き加えられたものである。言うまでもなく「第九」の最高潮は合唱が始まるここからだ。でもそれなら今までのは何だったのだ。ベートーヴェンはなぜ今までの音を否定するのだ。
「第九」はそんな厳しい否定の精神によって成り立っている。この厳しさに作品の本質を見る人たちの中には、日本では年末の風物詩となった「第九」に違和感を覚える人もいるという。日本人はベートーヴェンの魂と本当に向き合っているのだろうか、ということだろう。だが、見方を変えればこれほど「第九」が演奏されている国は世界にもないのであって(毎年、大晦日にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が演奏しているが)、日本に住む人はけっこう、ベートーヴェンの魂と向き合っているのだ。おそらくはその厳しい否定の精神ともども、僕たちは「第九」を愛しているのである。
ベートーヴェンが否定したものとは何か。この作品が書かれた当時、彼の周囲にあったものを考えてみる。その青年時代は、ゲーテ、シラーらによって打ち立てられた文学運動シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)と時期が重なっている。フランス革命とナポレオンの台頭、その死に至る一連の出来事は激しく彼の心を揺さぶったことだろう。そこに芽吹いたのは近代的な「市民」の意識である。神の時代は終わり、王の時代も過ぎ去ろうとしている。人は人として認められなければならない。それを呼びかける曲を書く時に、ベートーヴェンは自分が今立っている場所を明確に宣言したのだ。自分と世界の「これまで」を厳しく否定することで、「これから」の世界に踏み出そうとしたのである。第4楽章はその実現なのだ。
僕自身がこの作品に覚えるわずかな「変さ」は、おそらくはこうしたベートーヴェンの理念自体が、作品からはみ出してしまうほどの巨大な力を宿していることによる。その力が全容を現す瞬間が、まさにあの言葉なのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この作品が初演されたのは1824年。その時代背景を思う時、あらためて気づかされるのは、人間が自由というものを手にしてからまだ200年ほどにしかならないという事実である。しかもそれはまだ途上なのだ。そしてベートーヴェンその人について言うならば、この曲が完成された当時、彼は完全に聴力を失っていた。音楽家としてはもちろん、ひとりの人間として社交の機会を閉ざされたその寂しさはどれほどであっただろう。だからこの曲は、彼の人を恋うる曲でもある。無音の孤独の淵から人々に向かって微笑みを投げかける、ベートーヴェンの心の歌なのだと思う。
この作品と新鮮な形で向き合おうとするならば、あなたは少しだけ背筋を伸ばしてみるのがいいかも知れない。そして自分の心の中を少し整理して客席に座ってみる。そうすればなぜこの曲が年の瀬にこんなに愛されるのか、よくわかると思う。
「おお友よ、このような音ではなく!」その言葉がもし、わずかに重さを伴ってあなたの元に届いたとしたら、あなたもきっとベートーヴェンの魂に触れているのだ。
音楽ライター 逢坂 聖也
「プログラム・マガジン」2017年12月号掲載
写真左:ウィーン・ハイリゲンシュタット公園のベートーヴェン像
写真右:第九完成の家の銘板(ウィーン)
写真提供:長島喜一郎