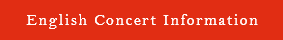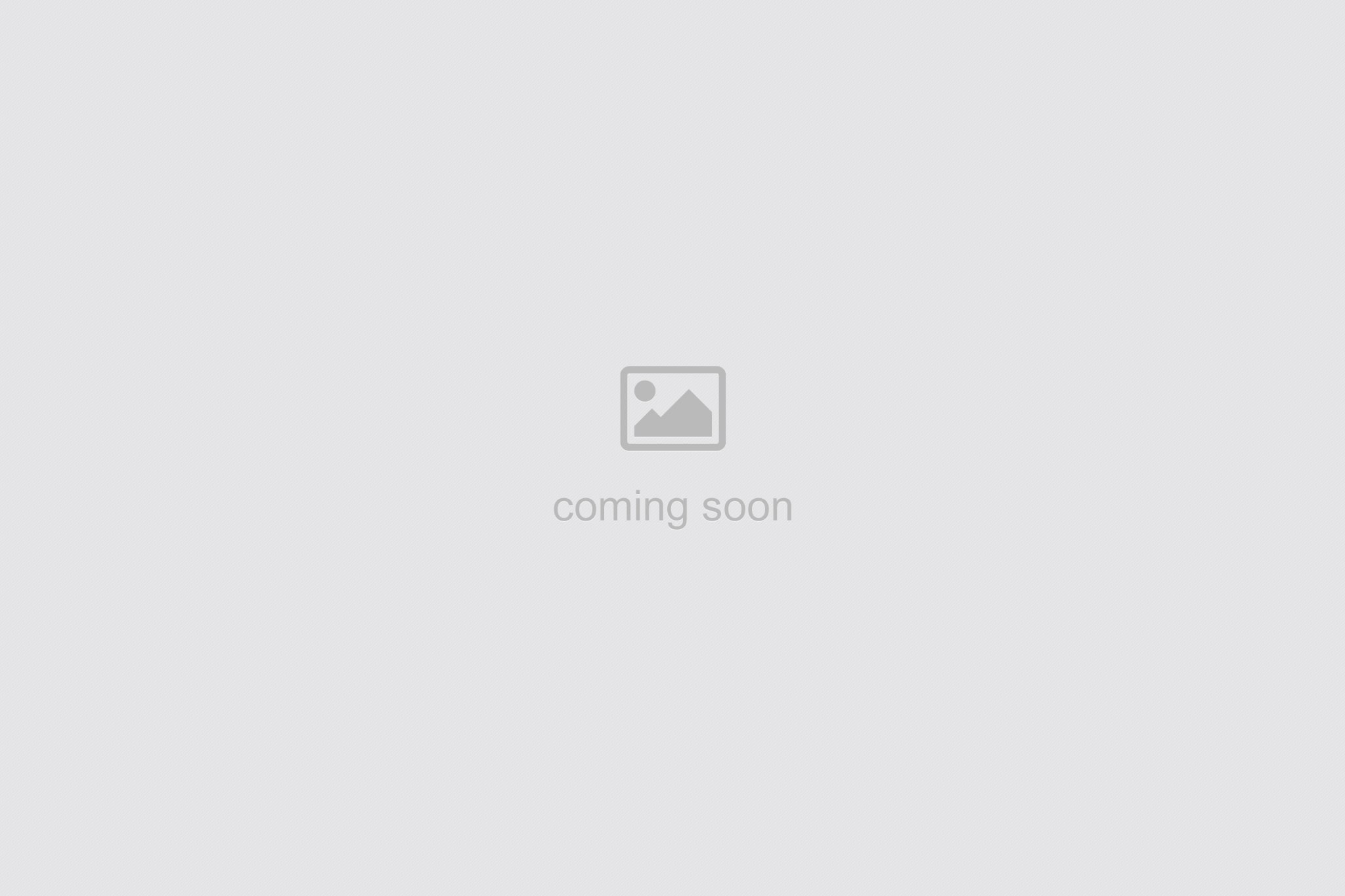エッセー(2018)
エッセー 時を止める音楽
2018-07-17
リヒャルト・シュトラウスのオペラの登場人物で最も魅力的なのは誰でしょう。もちろん答えは人によって様々でしょうが、『ばらの騎士』の元帥夫人(マルシャリン)を挙げる人が多いのではないでしょうか。元帥夫人はシュトラウスの作品だけでなく、あらゆるオペラの登場人物の中でも最も細やかな感情をもった深みのある人物のひとりと言ってよいでしょう。
元帥夫人は美しい容姿と暖かく寛大な心の持ち主であるだけでなく、自分の内面をしっかりと見つめ、思索し内省した末に、心の平安を見出します。その気高い姿は聴く人に深い感動を呼び起こします。元帥夫人の深い思索が端的にあらわれているのが第1幕のモノローグです。若い恋人オクタヴィアンが立ち去ったあと、孤独感に襲われた夫人は、時の流れに思いを馳せ、過ぎ去った時間を嘆きます。オクタヴィアンが戻って来ても、彼女の心は晴れません。
「時というものは不思議なもの。忙しく過ごしているときには、何とも思わないもの。でもふいに、時のことしか感じられなくなるの。私たちのまわりにも、私たちのなかにも、時は流れている。顔のなかにも、鏡のなかにも、私のこめかみのなかにも、時は流れているの。あなたと私の間にも、時は流れてゆくのよ、音もなく、砂時計のように」。そして、彼女は「ときどき夜中に起きて、時計をみんな、みんな止めてしまうの」と続けます。
『ばらの騎士』の舞台は18世紀半ばのウィーンです。当時の上流階級の結婚は家系を維持するため、子孫を残すためのものであり、愛情のない結婚も多かったのです。ですから、男たちは外で女性と遊ぶのは当たり前で、一方女性たちもそれなりに遊んでいたのです。夫の元帥はオペラ全曲を通じて全く登場せず、戦場で勇敢に戦っているのか、はたまたどこかで遊んでいるのかは曖昧にされています(オクタヴィアンは「元帥は今ごろ熊や山猫の狩りをしているんだ」と言っていますが、「狩り」の対象が何なのかは不明です)。元帥夫人は夫の留守中にオクタヴィアンと何度も夜を過ごしています。夫はそれにうすうす気づいているのでしょうが、放っておいていますし、召使いたちも決して騒ぎ立てたりはしません。召使いが朝食を持ってくるとき、ココアのカップは一つだけで、若い恋人は「いないこと」にして、淡々と仕事を進めるのです。不倫に関しては非常に寛容な時代だったと言えます。
シュトラウスは次のように述べています。「元帥夫人はせいぜい32歳の若く美しい女性でなければならない。彼女は機嫌の悪い時にふと、17歳のオクタヴィアンに対して自分が“年取った女”だと感じるのである。美しい元帥夫人にとって、オクタヴィアンは最初の恋人でもなければ、最後の恋人でもない。第1幕の幕切れでも、人生への悲劇的な別れといった感傷的な調子になってはならず、ウィーン風な優雅さと軽やかさをもって、片方の目だけで泣くように演じられなければならない」
元帥夫人が32歳というのは、現代の私たちにとっては意外に思われます。今の時代、32歳で「年取った女」と感じる女性はまずいないでしょう。もっとも、「年取った女」(die alte Frau、英語ならthe old woman)というのはシュトラウスも言うように、機嫌の悪い時にふと若いオクタヴィアンに対して抱く羨望と嫉妬が混ざった感情から出た言葉ととらえられるので、自嘲気味な「おばさん」くらいの意味にとった方がいいのではないかと思います。「オクタヴィアンは最初の恋人でもなければ、最後の恋人でもない」というシュトラウスの言葉通り、元帥夫人は決して「終わった人」ではありません。私はかつて、元帥夫人を39歳と考えると人物像がリアルに感じられるのではないかと書いたことがあります。もっとも今日では、それさえ現実味に乏しくなってきて、むしろアラフィフととらえてもいいのかもしれません。その辺は、聴き手のみなさんがそれぞれに感情移入して聴いてくださればいいわけで、それもまたオペラの楽しみのひとつと言えるでしょう。
元帥夫人はなぜこんなにも「時」にこだわるのでしょうか。それは彼女の誠実さのせいであり、誠実であるがゆえに、変わること、過去を忘れることに抵抗を感じるからです。本日のコンサートには登場しませんが、『ばらの騎士』の重要な登場人物であるオックス男爵は、元帥夫人とは対照的です。大恥をかき、花嫁を失いながらも、第3幕で豪快なワルツにのって意気揚々と退場するオックスは、「忘れる」ことに全く抵抗がありません。しかし、それは成長しない、生まれ変わらないということでもあります。元帥夫人は内省と思索の末に、孤独を克服し、諦念の中に幸福を見出し、人間として成長するのです。
全曲のクライマックス、第3幕の三重唱では、元帥夫人、オクタヴィアン、ゾフィー、3人それぞれの思いが陶酔的な音楽で歌われます。異なる歌詞を同時に歌うのは、オペラの真骨頂と言えます。もし芝居で登場人物が異なるせりふを全く同時にしゃべったら、何を言っているのかわからず、きたなく聞こえるだけになってしまうでしょう。しかし、オペラでは異なる歌詞が美しいハーモニーの中で溶け合って、崇高な調和の響きを紡ぎ出すのです。若い二人からやや離れて、哀しみをたたえた気高さを漂わせながら、暖かく二人を見守り、ゾフィーの父ファーニナルの「若い人たちとはこんなものなのですね」という言葉に、「そう、ね(Ja, ja.)」とだけ答えて立ち去って行く元帥夫人。三重唱から元帥夫人の退場までに経過する時間は、実はほんのわずかなのかもしれません。しかし、ここに音楽がつくと時が止まるのです。束の間の瞬間に現実を超えた持続性を与え、その瞬間を引き留めるのは、まさに音楽の魔術のなせるわざなのです。そして、こういう瞬間にこそ、シュトラウスは天上の調べのような至高の音楽を作り出します。聴き手は止まった時間の中を漂い、まるで無重力になって空中を浮遊しているかのような陶酔を味わい、そして元帥夫人の姿に深く共感するのです。この三重唱はシュトラウスの最高傑作のひとつであるとともに、オペラ史上に輝く屈指の名場面と言えるでしょう。
美しくも切なさをたたえた三重唱の後、オクタヴィアンとゾフィーの優しい感情に溢れた素朴な二重唱が続き、明るさを取り戻して全曲の幕が下ります。「片方の目だけで泣いて」退場した元帥夫人の微笑みが目に浮かぶような幕切れ。シュトラウスの音楽は、人間の誠実さをいとおしみ、高貴な精神を静かに讃えているように感じられないでしょうか。
元帥夫人は美しい容姿と暖かく寛大な心の持ち主であるだけでなく、自分の内面をしっかりと見つめ、思索し内省した末に、心の平安を見出します。その気高い姿は聴く人に深い感動を呼び起こします。元帥夫人の深い思索が端的にあらわれているのが第1幕のモノローグです。若い恋人オクタヴィアンが立ち去ったあと、孤独感に襲われた夫人は、時の流れに思いを馳せ、過ぎ去った時間を嘆きます。オクタヴィアンが戻って来ても、彼女の心は晴れません。
「時というものは不思議なもの。忙しく過ごしているときには、何とも思わないもの。でもふいに、時のことしか感じられなくなるの。私たちのまわりにも、私たちのなかにも、時は流れている。顔のなかにも、鏡のなかにも、私のこめかみのなかにも、時は流れているの。あなたと私の間にも、時は流れてゆくのよ、音もなく、砂時計のように」。そして、彼女は「ときどき夜中に起きて、時計をみんな、みんな止めてしまうの」と続けます。
『ばらの騎士』の舞台は18世紀半ばのウィーンです。当時の上流階級の結婚は家系を維持するため、子孫を残すためのものであり、愛情のない結婚も多かったのです。ですから、男たちは外で女性と遊ぶのは当たり前で、一方女性たちもそれなりに遊んでいたのです。夫の元帥はオペラ全曲を通じて全く登場せず、戦場で勇敢に戦っているのか、はたまたどこかで遊んでいるのかは曖昧にされています(オクタヴィアンは「元帥は今ごろ熊や山猫の狩りをしているんだ」と言っていますが、「狩り」の対象が何なのかは不明です)。元帥夫人は夫の留守中にオクタヴィアンと何度も夜を過ごしています。夫はそれにうすうす気づいているのでしょうが、放っておいていますし、召使いたちも決して騒ぎ立てたりはしません。召使いが朝食を持ってくるとき、ココアのカップは一つだけで、若い恋人は「いないこと」にして、淡々と仕事を進めるのです。不倫に関しては非常に寛容な時代だったと言えます。
シュトラウスは次のように述べています。「元帥夫人はせいぜい32歳の若く美しい女性でなければならない。彼女は機嫌の悪い時にふと、17歳のオクタヴィアンに対して自分が“年取った女”だと感じるのである。美しい元帥夫人にとって、オクタヴィアンは最初の恋人でもなければ、最後の恋人でもない。第1幕の幕切れでも、人生への悲劇的な別れといった感傷的な調子になってはならず、ウィーン風な優雅さと軽やかさをもって、片方の目だけで泣くように演じられなければならない」
元帥夫人が32歳というのは、現代の私たちにとっては意外に思われます。今の時代、32歳で「年取った女」と感じる女性はまずいないでしょう。もっとも、「年取った女」(die alte Frau、英語ならthe old woman)というのはシュトラウスも言うように、機嫌の悪い時にふと若いオクタヴィアンに対して抱く羨望と嫉妬が混ざった感情から出た言葉ととらえられるので、自嘲気味な「おばさん」くらいの意味にとった方がいいのではないかと思います。「オクタヴィアンは最初の恋人でもなければ、最後の恋人でもない」というシュトラウスの言葉通り、元帥夫人は決して「終わった人」ではありません。私はかつて、元帥夫人を39歳と考えると人物像がリアルに感じられるのではないかと書いたことがあります。もっとも今日では、それさえ現実味に乏しくなってきて、むしろアラフィフととらえてもいいのかもしれません。その辺は、聴き手のみなさんがそれぞれに感情移入して聴いてくださればいいわけで、それもまたオペラの楽しみのひとつと言えるでしょう。
元帥夫人はなぜこんなにも「時」にこだわるのでしょうか。それは彼女の誠実さのせいであり、誠実であるがゆえに、変わること、過去を忘れることに抵抗を感じるからです。本日のコンサートには登場しませんが、『ばらの騎士』の重要な登場人物であるオックス男爵は、元帥夫人とは対照的です。大恥をかき、花嫁を失いながらも、第3幕で豪快なワルツにのって意気揚々と退場するオックスは、「忘れる」ことに全く抵抗がありません。しかし、それは成長しない、生まれ変わらないということでもあります。元帥夫人は内省と思索の末に、孤独を克服し、諦念の中に幸福を見出し、人間として成長するのです。
全曲のクライマックス、第3幕の三重唱では、元帥夫人、オクタヴィアン、ゾフィー、3人それぞれの思いが陶酔的な音楽で歌われます。異なる歌詞を同時に歌うのは、オペラの真骨頂と言えます。もし芝居で登場人物が異なるせりふを全く同時にしゃべったら、何を言っているのかわからず、きたなく聞こえるだけになってしまうでしょう。しかし、オペラでは異なる歌詞が美しいハーモニーの中で溶け合って、崇高な調和の響きを紡ぎ出すのです。若い二人からやや離れて、哀しみをたたえた気高さを漂わせながら、暖かく二人を見守り、ゾフィーの父ファーニナルの「若い人たちとはこんなものなのですね」という言葉に、「そう、ね(Ja, ja.)」とだけ答えて立ち去って行く元帥夫人。三重唱から元帥夫人の退場までに経過する時間は、実はほんのわずかなのかもしれません。しかし、ここに音楽がつくと時が止まるのです。束の間の瞬間に現実を超えた持続性を与え、その瞬間を引き留めるのは、まさに音楽の魔術のなせるわざなのです。そして、こういう瞬間にこそ、シュトラウスは天上の調べのような至高の音楽を作り出します。聴き手は止まった時間の中を漂い、まるで無重力になって空中を浮遊しているかのような陶酔を味わい、そして元帥夫人の姿に深く共感するのです。この三重唱はシュトラウスの最高傑作のひとつであるとともに、オペラ史上に輝く屈指の名場面と言えるでしょう。
美しくも切なさをたたえた三重唱の後、オクタヴィアンとゾフィーの優しい感情に溢れた素朴な二重唱が続き、明るさを取り戻して全曲の幕が下ります。「片方の目だけで泣いて」退場した元帥夫人の微笑みが目に浮かぶような幕切れ。シュトラウスの音楽は、人間の誠実さをいとおしみ、高貴な精神を静かに讃えているように感じられないでしょうか。
鶴間 圭(音楽学)
写真左:
「ばらの騎士」のコンビ
脚本家のホフマンスタール(左)とR.シュトラウス
脚本家のホフマンスタール(左)とR.シュトラウス
写真右:
「ばらの騎士」の舞台写真(ザルツブルク音楽祭のプロダクション)
写真提供:ザルツブルク音楽祭事務局
写真提供:ザルツブルク音楽祭事務局
「プログラム・マガジン」2018年7・8月号掲載
エッセー(2017)
第九エッセー2017
2017-12-22
第九 エッセー
「おお友よ、このような音ではなく!」 ~第九が届けてくれるもの
初めて「第九」を知った中学生の頃、変な曲だと思った。実は今でも少し、そんな風に思っている。
第4楽章まで聴き進んで来て、その始まりの部分で第3楽章までの音楽はかき消されてしまう。チェロとコントラバスの忙しないモノローグによって。そして音楽が動き始めたところでバリトンが歌い出すのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この言葉は実はシラーの原詩にはなくて、ベートーヴェンによって書き加えられたものである。言うまでもなく「第九」の最高潮は合唱が始まるここからだ。でもそれなら今までのは何だったのだ。ベートーヴェンはなぜ今までの音を否定するのだ。
「第九」はそんな厳しい否定の精神によって成り立っている。この厳しさに作品の本質を見る人たちの中には、日本では年末の風物詩となった「第九」に違和感を覚える人もいるという。日本人はベートーヴェンの魂と本当に向き合っているのだろうか、ということだろう。だが、見方を変えればこれほど「第九」が演奏されている国は世界にもないのであって(毎年、大晦日にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が演奏しているが)、日本に住む人はけっこう、ベートーヴェンの魂と向き合っているのだ。おそらくはその厳しい否定の精神ともども、僕たちは「第九」を愛しているのである。
ベートーヴェンが否定したものとは何か。この作品が書かれた当時、彼の周囲にあったものを考えてみる。その青年時代は、ゲーテ、シラーらによって打ち立てられた文学運動シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)と時期が重なっている。フランス革命とナポレオンの台頭、その死に至る一連の出来事は激しく彼の心を揺さぶったことだろう。そこに芽吹いたのは近代的な「市民」の意識である。神の時代は終わり、王の時代も過ぎ去ろうとしている。人は人として認められなければならない。それを呼びかける曲を書く時に、ベートーヴェンは自分が今立っている場所を明確に宣言したのだ。自分と世界の「これまで」を厳しく否定することで、「これから」の世界に踏み出そうとしたのである。第4楽章はその実現なのだ。
僕自身がこの作品に覚えるわずかな「変さ」は、おそらくはこうしたベートーヴェンの理念自体が、作品からはみ出してしまうほどの巨大な力を宿していることによる。その力が全容を現す瞬間が、まさにあの言葉なのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この作品が初演されたのは1824年。その時代背景を思う時、あらためて気づかされるのは、人間が自由というものを手にしてからまだ200年ほどにしかならないという事実である。しかもそれはまだ途上なのだ。そしてベートーヴェンその人について言うならば、この曲が完成された当時、彼は完全に聴力を失っていた。音楽家としてはもちろん、ひとりの人間として社交の機会を閉ざされたその寂しさはどれほどであっただろう。だからこの曲は、彼の人を恋うる曲でもある。無音の孤独の淵から人々に向かって微笑みを投げかける、ベートーヴェンの心の歌なのだと思う。
この作品と新鮮な形で向き合おうとするならば、あなたは少しだけ背筋を伸ばしてみるのがいいかも知れない。そして自分の心の中を少し整理して客席に座ってみる。そうすればなぜこの曲が年の瀬にこんなに愛されるのか、よくわかると思う。
「おお友よ、このような音ではなく!」その言葉がもし、わずかに重さを伴ってあなたの元に届いたとしたら、あなたもきっとベートーヴェンの魂に触れているのだ。
この言葉は実はシラーの原詩にはなくて、ベートーヴェンによって書き加えられたものである。言うまでもなく「第九」の最高潮は合唱が始まるここからだ。でもそれなら今までのは何だったのだ。ベートーヴェンはなぜ今までの音を否定するのだ。
「第九」はそんな厳しい否定の精神によって成り立っている。この厳しさに作品の本質を見る人たちの中には、日本では年末の風物詩となった「第九」に違和感を覚える人もいるという。日本人はベートーヴェンの魂と本当に向き合っているのだろうか、ということだろう。だが、見方を変えればこれほど「第九」が演奏されている国は世界にもないのであって(毎年、大晦日にはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が演奏しているが)、日本に住む人はけっこう、ベートーヴェンの魂と向き合っているのだ。おそらくはその厳しい否定の精神ともども、僕たちは「第九」を愛しているのである。
ベートーヴェンが否定したものとは何か。この作品が書かれた当時、彼の周囲にあったものを考えてみる。その青年時代は、ゲーテ、シラーらによって打ち立てられた文学運動シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)と時期が重なっている。フランス革命とナポレオンの台頭、その死に至る一連の出来事は激しく彼の心を揺さぶったことだろう。そこに芽吹いたのは近代的な「市民」の意識である。神の時代は終わり、王の時代も過ぎ去ろうとしている。人は人として認められなければならない。それを呼びかける曲を書く時に、ベートーヴェンは自分が今立っている場所を明確に宣言したのだ。自分と世界の「これまで」を厳しく否定することで、「これから」の世界に踏み出そうとしたのである。第4楽章はその実現なのだ。
僕自身がこの作品に覚えるわずかな「変さ」は、おそらくはこうしたベートーヴェンの理念自体が、作品からはみ出してしまうほどの巨大な力を宿していることによる。その力が全容を現す瞬間が、まさにあの言葉なのだ。「おお友よ、このような音ではなく!」
この作品が初演されたのは1824年。その時代背景を思う時、あらためて気づかされるのは、人間が自由というものを手にしてからまだ200年ほどにしかならないという事実である。しかもそれはまだ途上なのだ。そしてベートーヴェンその人について言うならば、この曲が完成された当時、彼は完全に聴力を失っていた。音楽家としてはもちろん、ひとりの人間として社交の機会を閉ざされたその寂しさはどれほどであっただろう。だからこの曲は、彼の人を恋うる曲でもある。無音の孤独の淵から人々に向かって微笑みを投げかける、ベートーヴェンの心の歌なのだと思う。
この作品と新鮮な形で向き合おうとするならば、あなたは少しだけ背筋を伸ばしてみるのがいいかも知れない。そして自分の心の中を少し整理して客席に座ってみる。そうすればなぜこの曲が年の瀬にこんなに愛されるのか、よくわかると思う。
「おお友よ、このような音ではなく!」その言葉がもし、わずかに重さを伴ってあなたの元に届いたとしたら、あなたもきっとベートーヴェンの魂に触れているのだ。
音楽ライター 逢坂 聖也
「プログラム・マガジン」2017年12月号掲載
写真左:ウィーン・ハイリゲンシュタット公園のベートーヴェン像
写真右:第九完成の家の銘板(ウィーン)
写真提供:長島喜一郎