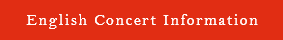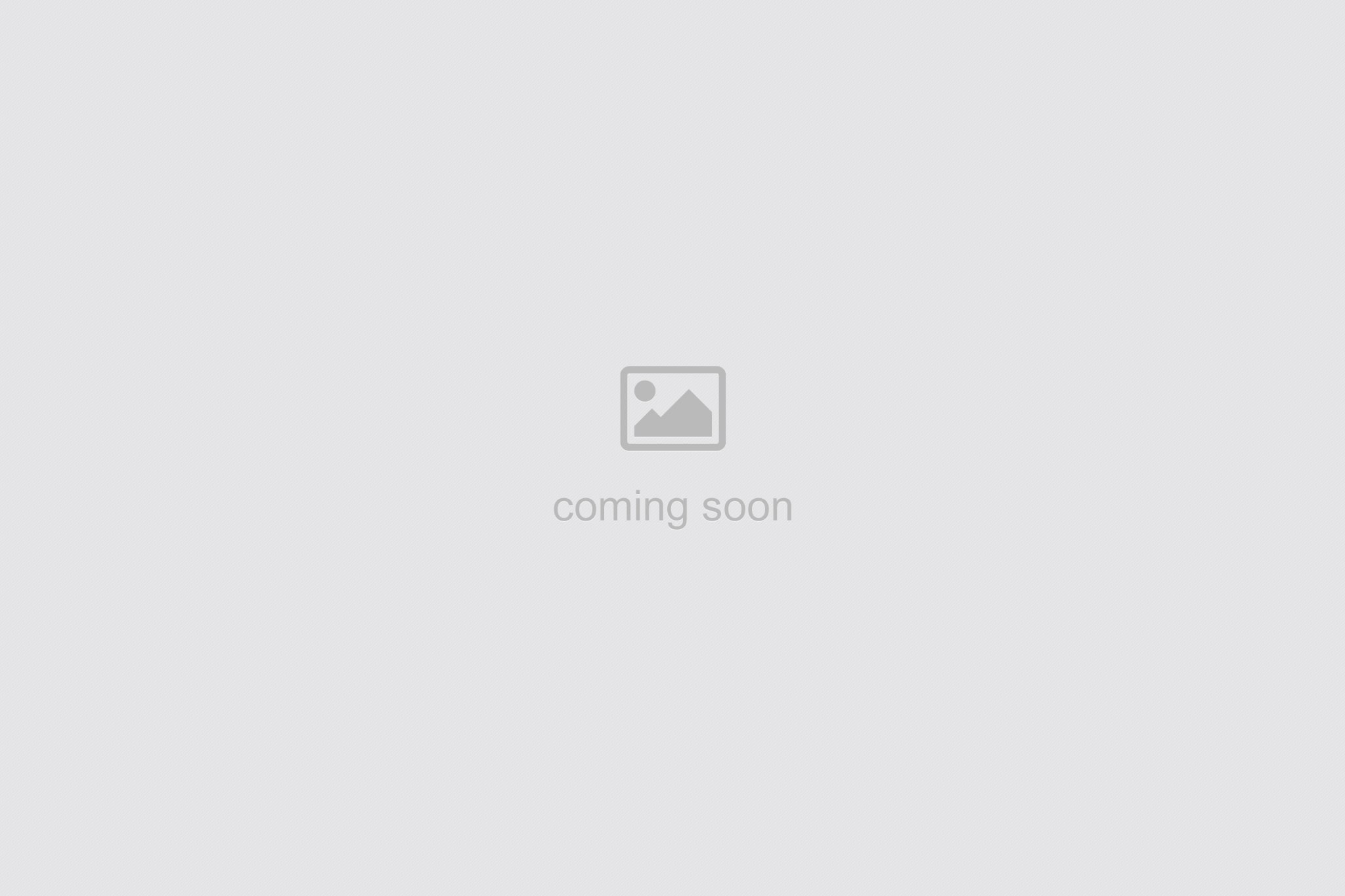インタビュー 早田 類(ヴィオラ首席奏者)
2022-10-27
ーヴァイオリンを始めたきっかけを教えてください。
母によると、5歳ぐらいの時に和波孝禧先生のリサイタルを聴いて、「ヴァイオリンをやりたい!」と言ったそうなんですけど、自分では覚えていないんです。母の幼なじみがヴァイオリニストの久保陽子先生で、母はどんなに大変なことなのかをそばで見ていたので、最初はなかなかやらせてもらえなかったんです。始めてみると、先生は厳しいしうまく弾けないしで、打ちひしがれた気分でした。だけど、いつか美しく弾けたらと思うと、離れられませんでした。
ーヴィオラに変わったのは、いつだったんですか?
東京藝術大学にヴァイオリンで入って、室内楽の授業でヴィオラに触れる中で、ヴィオラの音の方がヴァイオリンよりも好きだと思うようになりました。室内楽で内声を弾いているうちに、初めてこれだったら楽しいかもと思ったんです。その後、ヴィオラで大学院に入って、途中でフランスに留学し、ブリュノ・パスキエ先生のクラスに入りました。そこでは色々な個性の人がいて、それぞれの個性がリスペクトされていました。
もっと自分を出していいかなと思えました。先生がスイスのローザンヌ音楽院で教えることになって、ソリスト・ディプロマを取るために私も移り、起きてる間中、必死で練習するという毎日を過ごしました。最終試験の2週間後に、スペインのマドリード王立歌劇場のオーケストラのオーディションに合格して2004年から14年までの10年間、副首席奏者を務めました。
ーどんな音楽生活でしたか?
ひたすらオペラを弾く日々で、最初のうちはスペイン語もオペラの中の歌の歌詞もあまりわからないし、何よりも、予想外のことがたくさん起こるんですよ。歌手や指揮者が当日に変更なんてことはさらで、タイミングの違いなどに、その場で柔軟に対処しないといけない。最初の3年間はついていけないという感覚だったんですが、ある日突然「今日は何が起きるのかな」と思えるようになって、言葉も聞こえるようになったんです。そこから面白くなってきました。超一流の歌手たち、ドミンゴ、ヌッチ、ライモンディと、「これが音楽です!」と彼らの歌で否応なしに突きつけられる感じ。周りもそれに引っ張られて音楽が変わる。その経験は、今の音楽生活の中で種になっています。
一大阪交響楽団との出会いは?
友人が大阪交響楽団で弾いていて、帰国後にエキストラで呼んでいただいたのが、このオーケストラとの出会いでした。意見の交換は活発だし、風通しはいい。それぞれが個性的に演奏するオーケストラで、思いっきり弾いてもいい。関西はラテンの国に近いメンタリティがあって、思ったことを比較的自由に話せるからあまり違和感はありませんでした。オペラのオーケストラからシンフォニー・オーケストラに来て、最初は居心地が悪くて・・・オペラはピットの中で隠れていますが、今はステージの上で、常にお客様がたの視線にさらされていますから(笑)。
ーこれまで大阪交響楽団での印象に残る演奏会は何ですか?
トーマス・ザンデルリンクさん(第二代音楽監督・常任指揮者)との演奏会ですね(2020年2月7日・第237回
定期演奏会。ベートーヴェン交響曲第4番、ショスタコーヴィチ交響曲第10番)。オーケストラが持つ最大以上の力を引き出し、音のひとつひとつに命を吹き込んでいくマエストロの指揮に感動しながら弾いていました。
ーオーケストラでヴィオラを弾いていて良かったなと思える瞬間は?
さりげなく、あるべきところに、あるべき音、音楽を差し出すように心がけてはいますが、メロディラインがうまく乗っかってくれると「やった!」って思います。派手さや華やかさはなくても、いなくなってみて初めて気づかれる、くらいにさりげなくオーケストラを支える、縁の下の力持ちを目指したいと思っています。