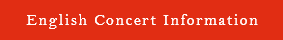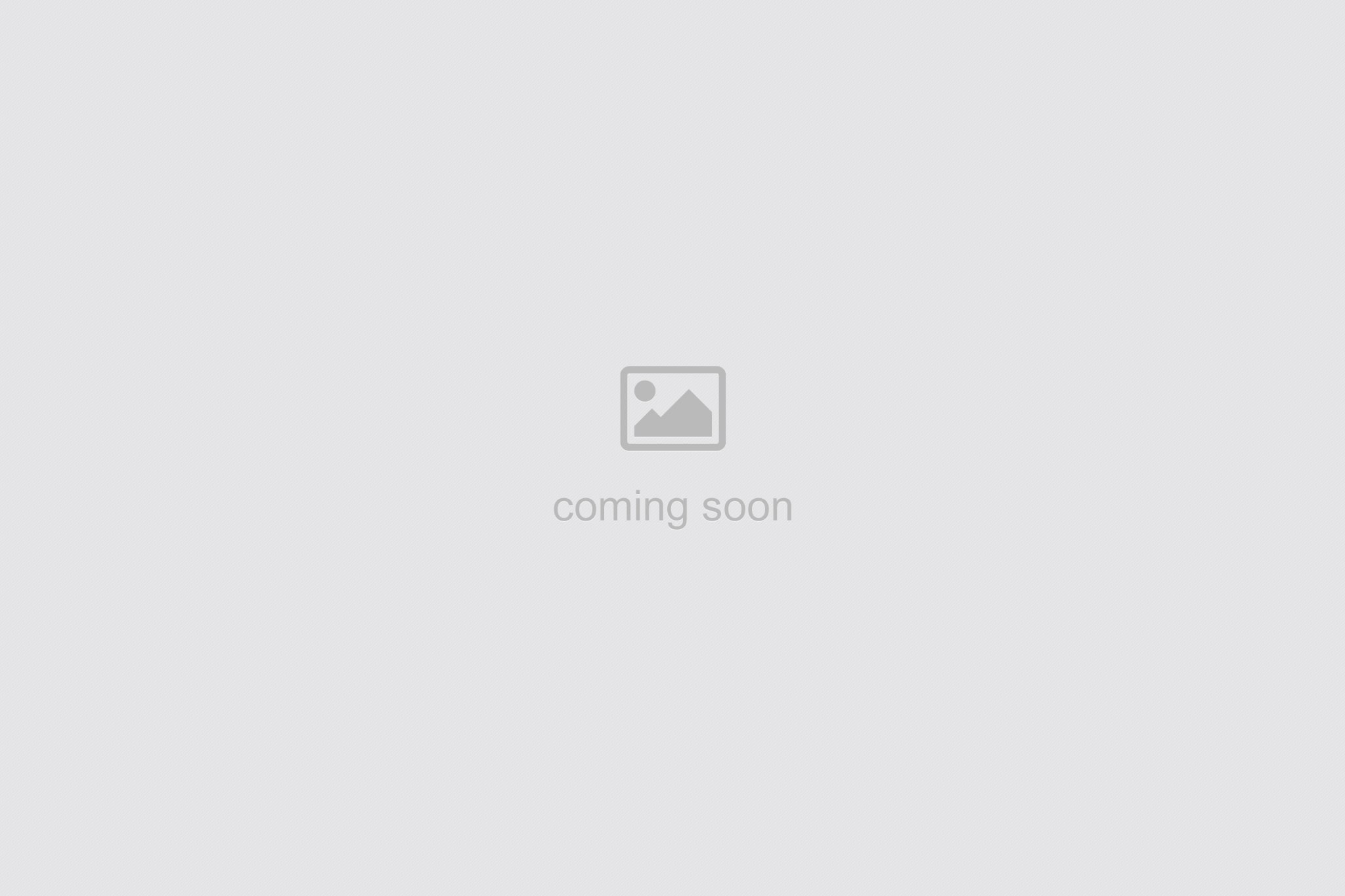テスト
創立35年記念シリーズ
【自然・人生・愛~マーラーとそのライヴァルたち④】
2015年12月17日(木)19時00分開演
〈セリオーソ〉の呼称で有名な、ベートーヴェンの『弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調』。彼がこの曲を書いたのは1810年から11年にかけてのことである。文字通り「セリオーソ=深刻」な曲想を湛えた作品であって、そこにはテレーゼ・マルファッティ(1792-1851)との恋愛が破局したことの影響を見て取る意見もあるほど。さらに言えば、ベートーヴェンが約10年もの間熱烈な想いを寄せたヨゼフィーネ・ダイム(1779-1821)が再婚したことも一層の追い打ちをかけた、という説も存在する。
ところで当四重奏曲は、マルファッティとの恋愛の一部始終を見守ったベートーヴェンの友人ニコラウス・ツマスカル(1759-1833)に捧げられている。しかも当時は、ナポレオン率いるフランス軍の度重なる攻撃により、ベートーヴェンの本拠地であったウィーンをはじめヨーロッパ各地が極度の緊張と不安の中に置かれていた。こうした事情も、この作品の深刻さにさらなる影響を与えているものと思われる。 (ただしベートーヴェン自身は作品そのものに〈セリオーソ〉というタイトルを与えたわけではなく、『カルテット・セリオーソ』という発想指示を第1楽章および第3楽章に書き込んでいることから、この呼称が生まれた。) それにしても、かくなる深刻な弦楽四重奏曲は、19世紀初頭においてきわめて異例の存在だった。というのも弦楽四重奏そのものが、元はといえば音楽愛好家同士が演奏して楽しむものだったからである。つまりは、深刻さよりも愉悦のほうが重視されるジャンルであったわけだが、そうした傾向にあえて背を向けるかのような作品をベートーヴェンが手がけた、といえるだろう。
何しろ作品全体を性格付けるヘ短調という調性そのものが、重苦しさや絶望を象徴している。それに加え、猛り狂うような激しさに溢れた第1楽章、一応長調(ニ長調)ではあるものの途中で荘重なフーガが出現し次の楽章へ切れ目なく続いてゆく第2楽章、激しさの中に賛美歌風(コラール風)のメロディが立ち現れる第3楽章、短調の楽想が延々と続くかと思いきや突如何の脈絡もなく長調に転じて終わる第4楽章といった具合に、当時の弦楽四重奏曲の常識を超えた作品となっている。
じっさいベートーヴェン自身、この曲にはひとかたならぬ思い入れがあったようで、それまでの弦楽四重奏曲のように初演を急ぐことなく、1814年に再び改訂の手を加えた後、初演がおこなわれている。しかも初演にあたったのは、腕利きのプロのヴァイオリン奏者として名高いイグナツ・シュパンツィヒ(1776-1830)率いるシュパンツィヒ四重奏団。ベートーヴェンは中期以降、プロでなければ十全に弾きこなせない演奏技術と音楽性を具えた弦楽四重奏曲を書き続けたが、当作品もそれに連なるものに他ならない。そしてこの作品を改訂した後、ベートーヴェンが次の弦楽四重奏曲を完成させるまでには、10年以上もの歳月が流れることとなった。(当作品の出版も、初演から2年も経った1816年になされたほどである。)
そんな、いわば弦楽四重奏を超えた弦楽四重奏を、コントラバスを含む弦楽合奏版に編曲したのがマーラーだ。指揮者として有名だった彼は、1897年にウィーン宮廷歌劇場の総監督、1898年からは同歌劇場管弦楽団の有志から成るウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任。1899年のシーズンには、この名門オーケストラにさらなる訓練を徹底するべく、有名な弦楽四重奏曲の弦楽合奏版(他にベートーヴェンの『弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調』とシューベルトの『弦楽四重奏曲第14番ニ短調〈死と乙女〉』。なお前者の楽譜は現在では行方不明となってしまっている。)を作ってはそれを演奏会で披露するという試みをおこなう。しかもそこには、作曲者本人の意思とは裏腹に歳月を経るごとに「お楽しみ」の要素が加わってしまった作品(やはり弦楽四重奏というジャンルの担い手は、一般的には音楽愛好家であるという状況がしかと存在していたため、作品そのものの芸術性よりかは、仲間同士の合奏という側面が重視されてしまう傾向がどうしても存在した)にあらためて正面から向き合い、作品本来の姿を蘇らせようという意図もあったにちがいない。
こうした状況の下、当作品のアレンジもおこなわれたわけだが、初演にあたってはオーケストラのメンバーからも聴衆からも非難轟々の嵐が巻き起こり、そのまま忘却の淵に沈んでしまった。なおマーラー編曲版による〈セリオーソ〉がウィーン・フィルの資料室の中から発見されたのは、実に初演から80年以上を経た1980年代のことである。
作曲:(オリジナル)1810-11年、(マーラー編曲版)1899年
初演:(オリジナル)1814年 ウィーン、
(マーラー編曲版)1899年 ウィーン
楽器編成:(マーラー編曲版)弦五部
少なくとも、1960年代に「マーラー・ルネッサンス」が起こるまで、マーラーの交響曲に対する一般的なイメージは、「幻想性と怪異さを具えたメルヘ
ン的作品」といったものではなかったか?ただし例えば『交響詩〈葬礼〉』に注目してみると、そうしたかつての見方もけっして的外れでなかったことが分かる。
『交響詩〈葬礼〉』が完成されたのは1888年。元々は構想中の交響曲の第1楽章として作られたものの、その後マーラーはこの計画自体を破棄。完成済の当作品を独立させ、1891年に『交響詩〈葬礼〉』と名付けて出版を画策したり、高名な指揮者ハンス・フォン・ビューロー(1830-94)に自身のピアノ演奏で聴かせて高評を期待したりするも、これらの目論見はことごとく失敗する。その後1894年に『交響曲第2番』を完成させるにあたって、彼はこの因縁の作品を改訂した上で、新作交響曲の第1楽章として組み込んだ。つまり『交響曲第2番』の第1楽章の原型が『交響詩〈葬礼〉』ということになるのだが、当交響詩自体はその後長らく忘れ去られてしまった。
それでは、『交響詩〈葬礼〉』と『交響曲第2番』の第1楽章との違いは何か?後者が前者よりも大きな編成を要していることはもとより、前者には登場しない楽節が20小節ほどにわたって展開部の途中に姿を現し、バッハの小フーガを思わせる動機が陰鬱に明滅する。後者においても残されることとなる『怒りの日』(死者の霊を弔うグレゴリオ聖歌)と並んで悪魔や死霊の集いすらも想起させる箇所に他ならず、さらにはシンバルの多用などを通じて魑魅魍魎のドンちゃん騒ぎにも似たグロテスクな響きに満ちたパッセージも聴かれる。
つまり『交響詩〈葬礼〉』においては、ロマン派の特徴の1つである「奇怪さ」(例えばウェーバーのオペラ『魔弾の射手』やドヴォルザーク晩年の一連の交響詩はその典型である)が、『交響曲第2番』の第1楽章よりも顕著に押し出されているといえるだろう。じっさい、〈葬礼〉というサブタイトルは、ポーランドの愛国詩人アダム・ミツキェヴィチ(1798-1855)の詩篇『父祖祭』を、マーラーの友人であるジークフリート・リピナー(1856-1911)がドイツ語に訳した際のタイトルに由来しているのだが、「父祖祭」とは元々ポーランド土着の死者の祭りであって、そこではあの世からこの世へ死霊が押し寄せ、まがまがしい狂宴を繰り広げる日と信じられていた。
そんな性格を色濃く宿した『交響詩〈葬礼〉』だが、改訂され『交響曲第2番』の中に新たに組み入れられるにあたって、「死」の威圧感や荘重さが押し出された。そして、マーラーの交響曲の特徴である「生と死の葛藤」というプログラムに相応しい上書きを施されていったのだった。
作曲:1888年
初演:1983年 ベルリン
楽器編成:フルート3(ピッコロ1持ち替え)、オーボエ2、
イングリッシュホルン1、クラリネット2、バスクラリネット1、
ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、
チューバ1、ティンパニ、トライアングル、シンバル、タムタム、
大太鼓、ハープ1、弦五部
『花の章』は、元々五楽章構成だった『交響曲第1番 ニ長調』の第2楽章だったものの、後にマーラー自身がこの交響曲を改訂してゆく中で削除された経緯を持つ作品として知られている。ところが話はさほど単純ではない。
マーラーは1883年から85年までドイツ中部のカッセルの王立劇場の次席楽長を務めた。この劇場でマーラーはオペラの指揮はもちろん、演劇用の音楽も書くといった具合に様々な仕事を手がけるのだが、その1つがヨーゼフ・フォン・シェッフェル(1826-86)のメルヘン戯曲『ゼッキンゲンのラッパ手』に曲を付けることだった。
この時書かれた曲が、『花の章』の原型と言われている。ただしカッセルの王立劇場のソプラノ歌手への片想いや、その後1886年に赴任したライプツィヒにおける人妻との許されざる恋など、マーラー自身激しい恋愛と失恋を繰り返す中で現在聴くことのできる『花の章』が形作られ、同時に『交響詩〈巨人〉』(『交響曲第1番』の初期の形)が成立していった。
というわけであえて誇張するならば、『花の章』が最初に存在し、それと連動しつつ『交響曲第1番』が生まれと言えるだろう。だがその後『交響詩
巨人〉』が数度に渡って改訂され、交響曲としての形式が整備されてゆく中で、1896年には交響曲誕生のきっかけとなった『花の章』そのものが削除され
、第二次世界大戦後まで忘却の淵に沈むこととなった。
なお『ゼッキンゲンのラッパ手』への付随音楽が基となっただけのことはあって、穏やかな楽想の中で、トランペットが儚くも幻想的な旋律を奏でるの
がこの曲の特徴。マーラーは救済に象徴される超越的な力を描く際に、必ずと言ってよいほど美しいトランペットの響きを用いたが、その萌芽はすでにこの作品にはっきりと聴き取れる。
作曲:1884-1888年(『交響詩〈巨人〉』の作曲とともに)
初演:1889年(『交響詩〈巨人〉』の初演とともに) ブダペスト
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、 ホルン4、トランペット1、ティンパニ、ハープ1、弦五部
『野の花々が私に語ること』は、1892年に構想されて以降、96年にかけて作曲された『交響曲第3番 ニ短調』の第2楽章。しかも交響曲の成立にあたっては、先に第2楽章から第6楽章が断続的に作られ、後からそれらをフィードバックさせる形で第1楽章が書かれた。
このように複雑な作曲の経緯があるためだろう。マーラー自身が『交響曲第3番』に統一感を与えるべく、各楽章に標題をつけて物語性を出し、第2楽章は『野の花々が私に語ること』と名付けられた。つまり逆に言えば、特に第2楽章以降はそれぞれの楽章の独立性や自己完結性が強いということであって、交響曲の全曲初演に先立ち第2楽章のみが初演されたのも頷ける。
こうした経緯があるからだろう。マーラー・ルネッサンスが始まる遥か前からマーラー作品に大きな関心を抱いていたベンジャミン・ブリテン(1913-
76)は1941年に当楽章を、しかもマーラーが最終的に削除した標題を用いたまま、単独の作品のごとく編曲した。
編曲のきっかけは、エルヴィン・シュタイン(1885-1958)からの依頼。自身マーラーの交響曲の編曲等を通じその普及に務めたシュタインだったが、ユダヤ人ということでナチスに追われて故郷のオーストリアからイギリスへ亡命し、ロンドンの楽譜出版社ブージ&ホークスに務めることとなる。そうした状況の中で、彼は当時ほとんど演奏されることのなかったマーラーの『交響曲第3番』の一部が小編成のオーケストラ用に編曲され広まることを期待しつつ、気鋭の作曲家だったブリテンに編曲を依頼したのである。
なお、『交響曲第3番』の第2楽章以降を見ると、若き日のマーラーが愛した詩集『少年の魔法の角笛』のテクストを用いた声楽曲…第5楽章と元々存在していた第7楽章…が含まれている。『少年の魔法の角笛』は、それこそ「幻想性と怪異さを具えたメルヘン的作品」だが、こうした要素を当作品も豊かに宿しているといえよう。優雅なメヌエットの体裁を取りつつレントラーを思わせる鄙びた味わいの主部と対象を成して、中間部では目まぐるしい変拍子に中にあって曲想は緊迫感を増し、百鬼夜行の音楽が明滅する。
作曲:1892-1896年(『交響曲第3番 ニ短調』の作曲とともに)
初演:1896年 ベルリン
楽器編成(ブリテン編曲版):フルート2(ピッコロ1持ち替え)、 オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、
トランペット3、タンバリン1、トライアングル1、シンバル1、 ルート1、グロッケンシュピール1、ハープ1、弦五部
『アダージョ』は、1910年に着手され、マーラー自身の死によって未完のまま残された『交響曲第10番 嬰ヘ長調』の第1楽章として書かれたもの。五楽章構成の作品として考えられていた当交響曲中、唯一この楽章だけはオーケストレーションが最初から最後までマーラー自身手によって施されていたため、単独で演奏されることも多い。(ただし実際に自作を演奏する際、マーラーは実演の結果から学んだ情報を元に楽譜を細かく訂正した上で、それを完成版として出版することを繰り返してきた。そうした意味においては、当楽章も『交響詩〈葬礼〉』と同様、マーラーが実演においてその響きを耳にすることのなかった作品として、完全な意味で「完成した」とはいえない状態にあるともいえよう。)
作曲当時のマーラーは、10年ほど連れ添った妻のアルマ(1879-1964)の気持ちが様々なストレスゆえに自分から離れ、建築家のヴァルター・グロピウス(1883-1969)へと移っていることを知り、大いに心を痛めていた。また1907年にウィーンの宮廷歌劇場総監督の地位を辞した後、ニューヨークを新た
な本拠地として活躍を始めたものの(といっても夏の休暇には必ずヨーロッパへ戻っていたのだが)、徐々に新天地での仕事にも問題を抱えるようになっていた。さらに自身の健康状態の悪化も加わり、彼の生活は…指揮者としての名声とは裏腹に…苦悩に包まれていた。
なお『アダージョ』は自由なソナタ形式で書かれており、調性すらも定かならぬヴィオラによる長大な序奏(序奏部分については「アンダンテ」と指定されている)に続き、アダージョの主部が登場。吹き上がるような憧れや嘆きを宿した第1主題と、マーラーの若き日からのトレードマークとも言える奇怪なメルヘン性を湛えた第2主題が現れる提示部、第2主題が形を変えて脅迫観念のように明滅する展開部、静謐な響きの中に突如破滅を想起させる不協和音が容赦なく立ち現れる再現部が続く。
作曲:1910年
初演:1924年 ウィーン
編成:フルート3(ピッコロ1持ち替え)、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ1、ハープ1、弦五部
(C) 小宮正安 (ヨーロッパ文化史研究家・横浜国立大学教授 )
(無断転載を禁じる)
じっさいベートーヴェン自身、この曲にはひとかたならぬ思い入れがあったようで、それまでの弦楽四重奏曲のように初演を急ぐことなく、1814年に再び改訂の手を加えた後、初演がおこなわれている。しかも初演にあたったのは、腕利きのプロのヴァイオリン奏者として名高いイグナツ・シュパンツィヒ(1776-1830)率いるシュパンツィヒ四重奏団。ベートーヴェンは中期以降、プロでなければ十全に弾きこなせない演奏技術と音楽性を具えた弦楽四重奏曲を書き続けたが、当作品もそれに連なるものに他ならない。そしてこの作品を改訂した後、ベートーヴェンが次の弦楽四重奏曲を完成させるまでには、10年以上もの歳月が流れることとなった。(当作品の出版も、初演から2年も経った1816年になされたほどである。)
そんな、いわば弦楽四重奏を超えた弦楽四重奏を、コントラバスを含む弦楽合奏版に編曲したのがマーラーだ。指揮者として有名だった彼は、1897年にウィーン宮廷歌劇場の総監督、1898年からは同歌劇場管弦楽団の有志から成るウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任。1899年のシーズンには、この名門オーケストラにさらなる訓練を徹底するべく、有名な弦楽四重奏曲の弦楽合奏版(他にベートーヴェンの『弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調』とシューベルトの『弦楽四重奏曲第14番ニ短調〈死と乙女〉』。なお前者の楽譜は現在では行方不明となってしまっている。)を作ってはそれを演奏会で披露するという試みをおこなう。しかもそこには、作曲者本人の意思とは裏腹に歳月を経るごとに「お楽しみ」の要素が加わってしまった作品(やはり弦楽四重奏というジャンルの担い手は、一般的には音楽愛好家であるという状況がしかと存在していたため、作品そのものの芸術性よりかは、仲間同士の合奏という側面が重視されてしまう傾向がどうしても存在した)にあらためて正面から向き合い、作品本来の姿を蘇らせようという意図もあったにちがいない。
こうした状況の下、当作品のアレンジもおこなわれたわけだが、初演にあたってはオーケストラのメンバーからも聴衆からも非難轟々の嵐が巻き起こり、そのまま忘却の淵に沈んでしまった。なおマーラー編曲版による〈セリオーソ〉がウィーン・フィルの資料室の中から発見されたのは、実に初演から80年以上を経た1980年代のことである。
作曲:(オリジナル)1810-11年、(マーラー編曲版)1899年
初演:(オリジナル)1814年 ウィーン、
(マーラー編曲版)1899年 ウィーン
楽器編成:(マーラー編曲版)弦五部
少なくとも、1960年代に「マーラー・ルネッサンス」が起こるまで、マーラーの交響曲に対する一般的なイメージは、「幻想性と怪異さを具えたメルヘ
ン的作品」といったものではなかったか?ただし例えば『交響詩〈葬礼〉』に注目してみると、そうしたかつての見方もけっして的外れでなかったことが分かる。
『交響詩〈葬礼〉』が完成されたのは1888年。元々は構想中の交響曲の第1楽章として作られたものの、その後マーラーはこの計画自体を破棄。完成済の当作品を独立させ、1891年に『交響詩〈葬礼〉』と名付けて出版を画策したり、高名な指揮者ハンス・フォン・ビューロー(1830-94)に自身のピアノ演奏で聴かせて高評を期待したりするも、これらの目論見はことごとく失敗する。その後1894年に『交響曲第2番』を完成させるにあたって、彼はこの因縁の作品を改訂した上で、新作交響曲の第1楽章として組み込んだ。つまり『交響曲第2番』の第1楽章の原型が『交響詩〈葬礼〉』ということになるのだが、当交響詩自体はその後長らく忘れ去られてしまった。
それでは、『交響詩〈葬礼〉』と『交響曲第2番』の第1楽章との違いは何か?後者が前者よりも大きな編成を要していることはもとより、前者には登場しない楽節が20小節ほどにわたって展開部の途中に姿を現し、バッハの小フーガを思わせる動機が陰鬱に明滅する。後者においても残されることとなる『怒りの日』(死者の霊を弔うグレゴリオ聖歌)と並んで悪魔や死霊の集いすらも想起させる箇所に他ならず、さらにはシンバルの多用などを通じて魑魅魍魎のドンちゃん騒ぎにも似たグロテスクな響きに満ちたパッセージも聴かれる。
つまり『交響詩〈葬礼〉』においては、ロマン派の特徴の1つである「奇怪さ」(例えばウェーバーのオペラ『魔弾の射手』やドヴォルザーク晩年の一連の交響詩はその典型である)が、『交響曲第2番』の第1楽章よりも顕著に押し出されているといえるだろう。じっさい、〈葬礼〉というサブタイトルは、ポーランドの愛国詩人アダム・ミツキェヴィチ(1798-1855)の詩篇『父祖祭』を、マーラーの友人であるジークフリート・リピナー(1856-1911)がドイツ語に訳した際のタイトルに由来しているのだが、「父祖祭」とは元々ポーランド土着の死者の祭りであって、そこではあの世からこの世へ死霊が押し寄せ、まがまがしい狂宴を繰り広げる日と信じられていた。
そんな性格を色濃く宿した『交響詩〈葬礼〉』だが、改訂され『交響曲第2番』の中に新たに組み入れられるにあたって、「死」の威圧感や荘重さが押し出された。そして、マーラーの交響曲の特徴である「生と死の葛藤」というプログラムに相応しい上書きを施されていったのだった。
作曲:1888年
初演:1983年 ベルリン
楽器編成:フルート3(ピッコロ1持ち替え)、オーボエ2、
イングリッシュホルン1、クラリネット2、バスクラリネット1、
ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、
チューバ1、ティンパニ、トライアングル、シンバル、タムタム、
大太鼓、ハープ1、弦五部
『花の章』は、元々五楽章構成だった『交響曲第1番 ニ長調』の第2楽章だったものの、後にマーラー自身がこの交響曲を改訂してゆく中で削除された経緯を持つ作品として知られている。ところが話はさほど単純ではない。
マーラーは1883年から85年までドイツ中部のカッセルの王立劇場の次席楽長を務めた。この劇場でマーラーはオペラの指揮はもちろん、演劇用の音楽も書くといった具合に様々な仕事を手がけるのだが、その1つがヨーゼフ・フォン・シェッフェル(1826-86)のメルヘン戯曲『ゼッキンゲンのラッパ手』に曲を付けることだった。
この時書かれた曲が、『花の章』の原型と言われている。ただしカッセルの王立劇場のソプラノ歌手への片想いや、その後1886年に赴任したライプツィヒにおける人妻との許されざる恋など、マーラー自身激しい恋愛と失恋を繰り返す中で現在聴くことのできる『花の章』が形作られ、同時に『交響詩〈巨人〉』(『交響曲第1番』の初期の形)が成立していった。
というわけであえて誇張するならば、『花の章』が最初に存在し、それと連動しつつ『交響曲第1番』が生まれと言えるだろう。だがその後『交響詩
巨人〉』が数度に渡って改訂され、交響曲としての形式が整備されてゆく中で、1896年には交響曲誕生のきっかけとなった『花の章』そのものが削除され
、第二次世界大戦後まで忘却の淵に沈むこととなった。
なお『ゼッキンゲンのラッパ手』への付随音楽が基となっただけのことはあって、穏やかな楽想の中で、トランペットが儚くも幻想的な旋律を奏でるの
がこの曲の特徴。マーラーは救済に象徴される超越的な力を描く際に、必ずと言ってよいほど美しいトランペットの響きを用いたが、その萌芽はすでにこの作品にはっきりと聴き取れる。
作曲:1884-1888年(『交響詩〈巨人〉』の作曲とともに)
初演:1889年(『交響詩〈巨人〉』の初演とともに) ブダペスト
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、 ホルン4、トランペット1、ティンパニ、ハープ1、弦五部
『野の花々が私に語ること』は、1892年に構想されて以降、96年にかけて作曲された『交響曲第3番 ニ短調』の第2楽章。しかも交響曲の成立にあたっては、先に第2楽章から第6楽章が断続的に作られ、後からそれらをフィードバックさせる形で第1楽章が書かれた。
このように複雑な作曲の経緯があるためだろう。マーラー自身が『交響曲第3番』に統一感を与えるべく、各楽章に標題をつけて物語性を出し、第2楽章は『野の花々が私に語ること』と名付けられた。つまり逆に言えば、特に第2楽章以降はそれぞれの楽章の独立性や自己完結性が強いということであって、交響曲の全曲初演に先立ち第2楽章のみが初演されたのも頷ける。
こうした経緯があるからだろう。マーラー・ルネッサンスが始まる遥か前からマーラー作品に大きな関心を抱いていたベンジャミン・ブリテン(1913-
76)は1941年に当楽章を、しかもマーラーが最終的に削除した標題を用いたまま、単独の作品のごとく編曲した。
編曲のきっかけは、エルヴィン・シュタイン(1885-1958)からの依頼。自身マーラーの交響曲の編曲等を通じその普及に務めたシュタインだったが、ユダヤ人ということでナチスに追われて故郷のオーストリアからイギリスへ亡命し、ロンドンの楽譜出版社ブージ&ホークスに務めることとなる。そうした状況の中で、彼は当時ほとんど演奏されることのなかったマーラーの『交響曲第3番』の一部が小編成のオーケストラ用に編曲され広まることを期待しつつ、気鋭の作曲家だったブリテンに編曲を依頼したのである。
なお、『交響曲第3番』の第2楽章以降を見ると、若き日のマーラーが愛した詩集『少年の魔法の角笛』のテクストを用いた声楽曲…第5楽章と元々存在していた第7楽章…が含まれている。『少年の魔法の角笛』は、それこそ「幻想性と怪異さを具えたメルヘン的作品」だが、こうした要素を当作品も豊かに宿しているといえよう。優雅なメヌエットの体裁を取りつつレントラーを思わせる鄙びた味わいの主部と対象を成して、中間部では目まぐるしい変拍子に中にあって曲想は緊迫感を増し、百鬼夜行の音楽が明滅する。
作曲:1892-1896年(『交響曲第3番 ニ短調』の作曲とともに)
初演:1896年 ベルリン
楽器編成(ブリテン編曲版):フルート2(ピッコロ1持ち替え)、 オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、
トランペット3、タンバリン1、トライアングル1、シンバル1、 ルート1、グロッケンシュピール1、ハープ1、弦五部
『アダージョ』は、1910年に着手され、マーラー自身の死によって未完のまま残された『交響曲第10番 嬰ヘ長調』の第1楽章として書かれたもの。五楽章構成の作品として考えられていた当交響曲中、唯一この楽章だけはオーケストレーションが最初から最後までマーラー自身手によって施されていたため、単独で演奏されることも多い。(ただし実際に自作を演奏する際、マーラーは実演の結果から学んだ情報を元に楽譜を細かく訂正した上で、それを完成版として出版することを繰り返してきた。そうした意味においては、当楽章も『交響詩〈葬礼〉』と同様、マーラーが実演においてその響きを耳にすることのなかった作品として、完全な意味で「完成した」とはいえない状態にあるともいえよう。)
作曲当時のマーラーは、10年ほど連れ添った妻のアルマ(1879-1964)の気持ちが様々なストレスゆえに自分から離れ、建築家のヴァルター・グロピウス(1883-1969)へと移っていることを知り、大いに心を痛めていた。また1907年にウィーンの宮廷歌劇場総監督の地位を辞した後、ニューヨークを新た
な本拠地として活躍を始めたものの(といっても夏の休暇には必ずヨーロッパへ戻っていたのだが)、徐々に新天地での仕事にも問題を抱えるようになっていた。さらに自身の健康状態の悪化も加わり、彼の生活は…指揮者としての名声とは裏腹に…苦悩に包まれていた。
なお『アダージョ』は自由なソナタ形式で書かれており、調性すらも定かならぬヴィオラによる長大な序奏(序奏部分については「アンダンテ」と指定されている)に続き、アダージョの主部が登場。吹き上がるような憧れや嘆きを宿した第1主題と、マーラーの若き日からのトレードマークとも言える奇怪なメルヘン性を湛えた第2主題が現れる提示部、第2主題が形を変えて脅迫観念のように明滅する展開部、静謐な響きの中に突如破滅を想起させる不協和音が容赦なく立ち現れる再現部が続く。
作曲:1910年
初演:1924年 ウィーン
編成:フルート3(ピッコロ1持ち替え)、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ1、ハープ1、弦五部
(C) 小宮正安 (ヨーロッパ文化史研究家・横浜国立大学教授 )
(無断転載を禁じる)