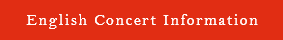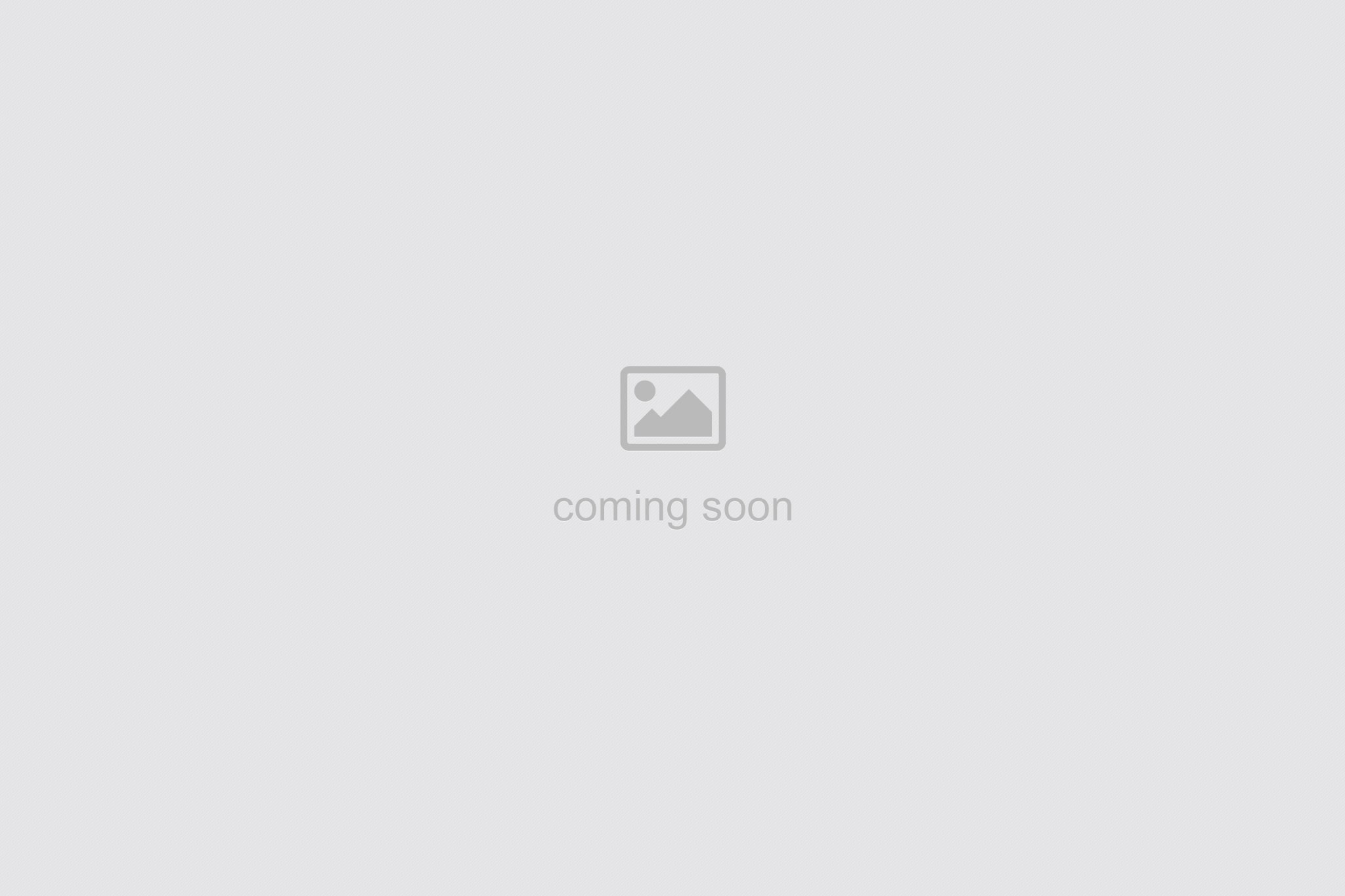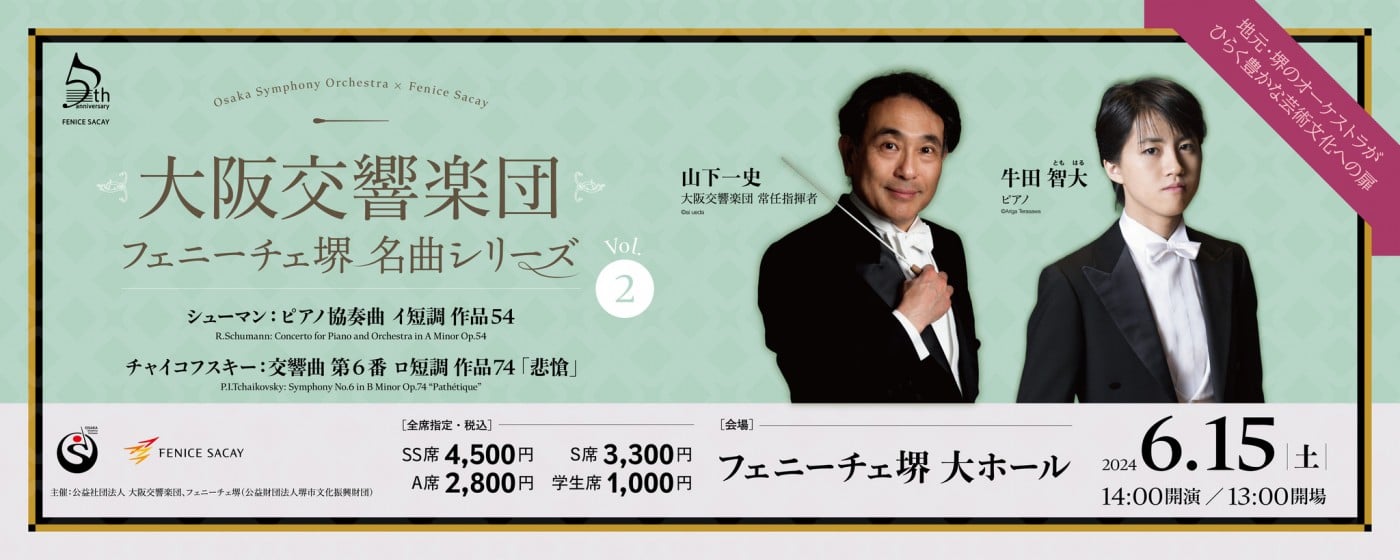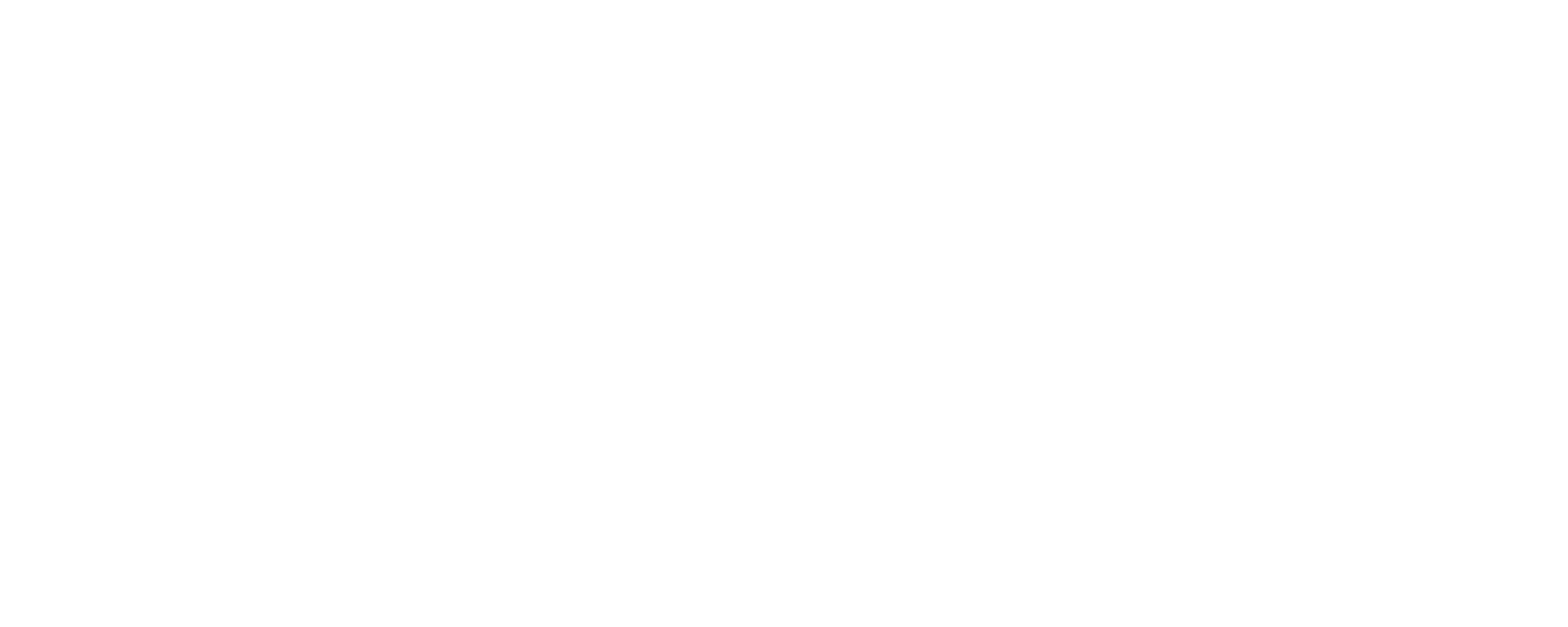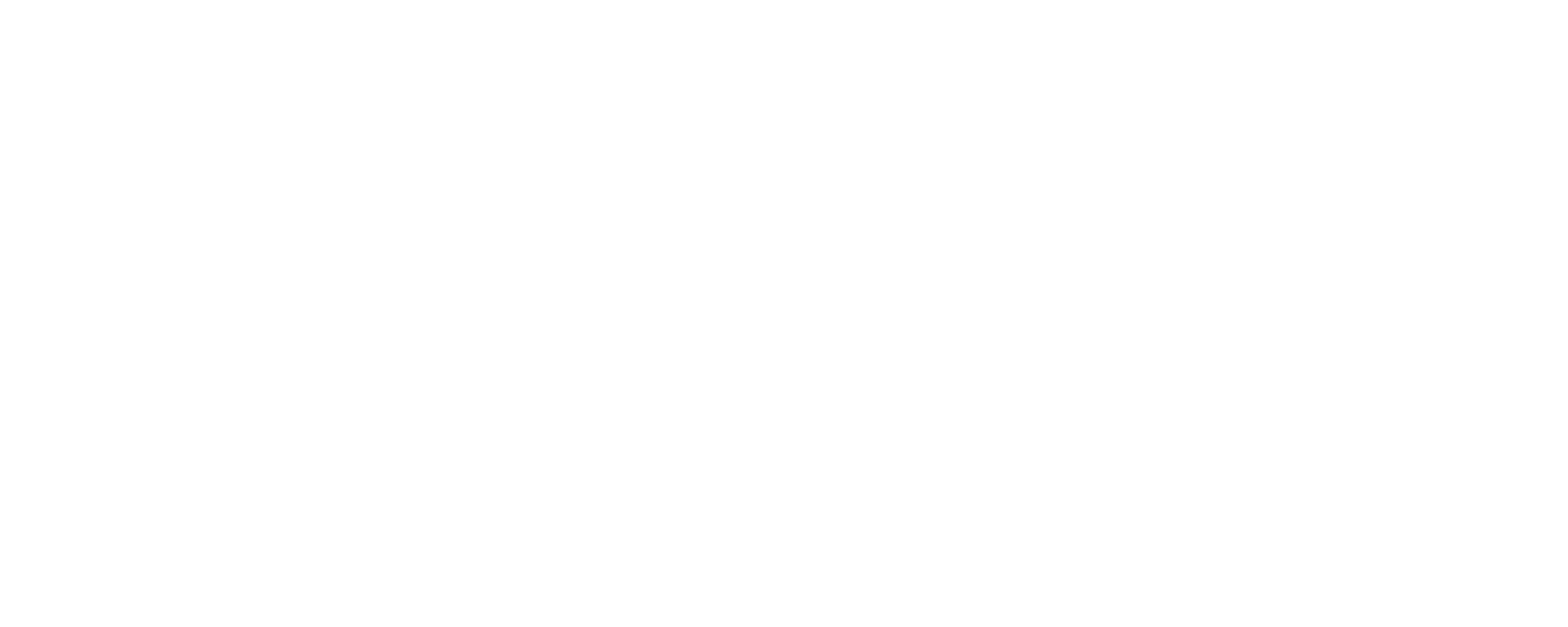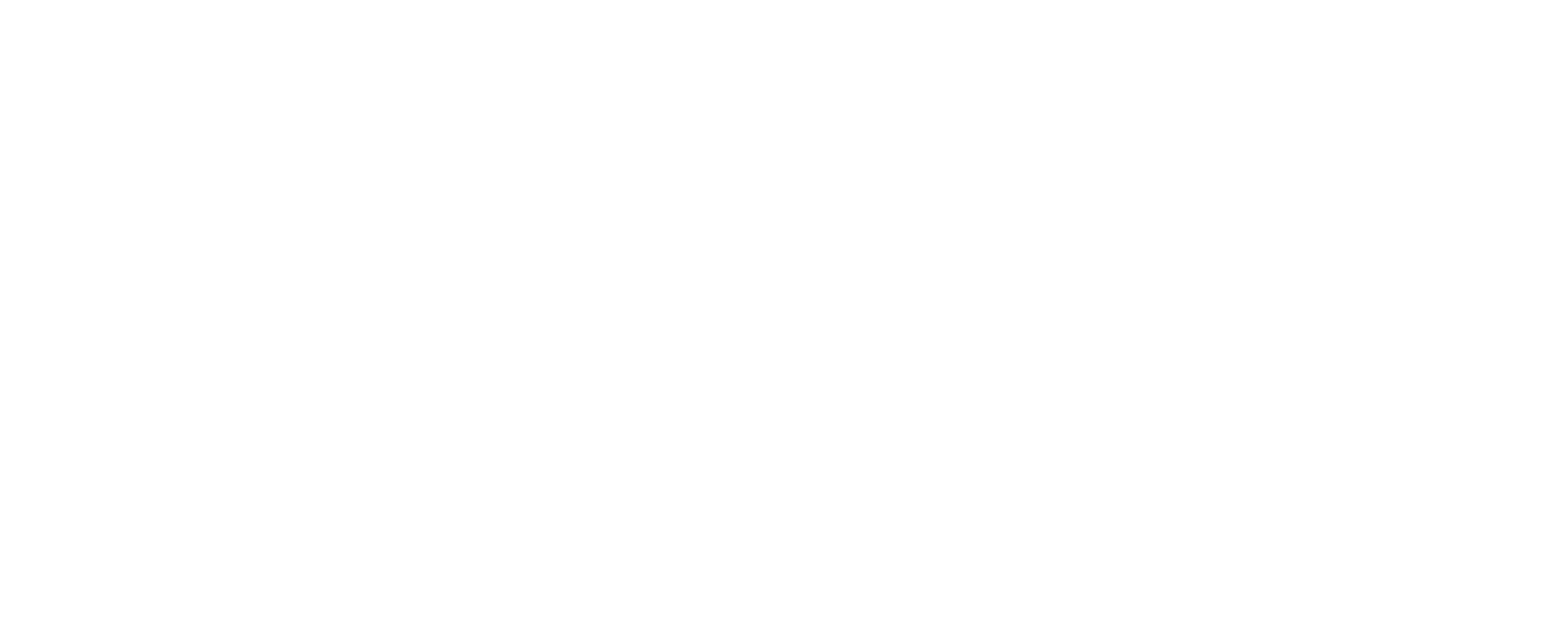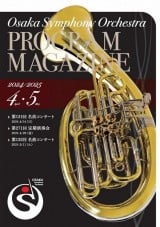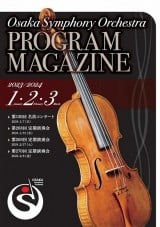TICKET
チケット販売情報
チケット販売情報
次のコンサート
第271回 定期演奏会
第272回 定期演奏会
第273回 定期演奏会
第273回 定期演奏会
「スラヴの世界から」
ドヴォルザーク没後120年
2024年 7月 5日(金)
ザ・シンフォニーホール
19:00開演/18:00開場
指揮/ジェイソン・ライ
チェロ/パヴェル・ゴムツィアコフ
【常任指揮者 山下一史からメッセージ】 第271回定期演奏会「外山雄三追悼」
4/26開催 第271回定期演奏会「外山雄三追悼」に向けて常任指揮者 山下一史が外山雄三さんとのエピソードや演奏会に込める想いを語りました。